journal
北が呼んでいる
2025.03.03
( Nordic Journal )

人に、故郷と呼べる場所は果たしていくつあるのだろうか。
生まれた場所や育った場所、好きな場所や好きだった場所、あるいは好きではなかった場所。昨日歩いたあの場所、いま立っているこの場所。
それは、現在地から振り返ってみればかけがえのない特別な“領域”であるのだけど、あの日、あの場所で過ごした時間は均質的な流れの一部に過ぎなくて、それがいつしか大切な存在に変わるだなんて少しも想像していなかったように思う。



ふと、北の空気を想い出すことがあります。
かつての滞在では、(右往曲折がありながらも)春夏秋冬をこの地で過ごすことができましたが、それは、土地の空気を身体に染み込ませるには十分な時間でした。日本に戻ればその空気を恋しく感じてしまうし、再びフィンランドに降り立つと、どこか懐かしさすら感じます。フィンランドに「来た」のではなくて「帰って来た」と、次第にそう思うようにもなりました。かつての滞在では、(右往曲折がありながらも)春夏秋冬をこの地で過ごすことができましたが、それは、土地の空気を身体に染み込ませるには十分な時間でした。日本に戻ればその空気を恋しく感じてしまうし、再びフィンランドに降り立つと、どこか懐かしさすら感じます。
フィンランドに「来た」のではなくて「帰って来た」と、次第にそう思うようにもなりました。



とはいえ現実を見れば、フィンランドの住民権を持たない以上は結局旅人であることに変わりはなくて、疲れた体で入国審査の長い列に並び、旅の目的をひと言ふた言で答え続けなければならないわけです。これからも。
「どれだけ住めばその地を故郷と呼べるのか」という問いと「旅人はいつ住民になり得るのか」という問いは、非なるようでどこか似ています。曖昧なものはいつまでも曖昧なままでも構わないと思いますが、何かを定義することによってそれが人間の孤独の小さな救いとなるのであれば、それもまた一つの美しい可能性だと思います。
2022年のヘルシンキデザインウィークのタイトルは「We are open」でした。具体的でありながらも抽象的なこの言葉は、まるで現代のフィンランドそのものをあらわしているようです。



人の生において、「ただそこにいる」ということを肯定してくれる存在はとても尊いものです。それは、とある言葉かもしれないし、近くの友人かもしれない。雄大な自然かもしれないし、ある特定の場所のことかもしれない。

ひとりひとりにきっとある、そういう特別な領域こそがその人にとっての故郷なのでしょう。帰る場所が、帰るべき場所があれと願えばこそ、その場所は記憶の中で生き続けるのです。



記憶の忘却はいつも静かに、しかし確かに進行していて、気付かぬうちに手のひらから離れてゆく。ややもすれば忘れ去られてしまう。空に解き放たれた風船のように。



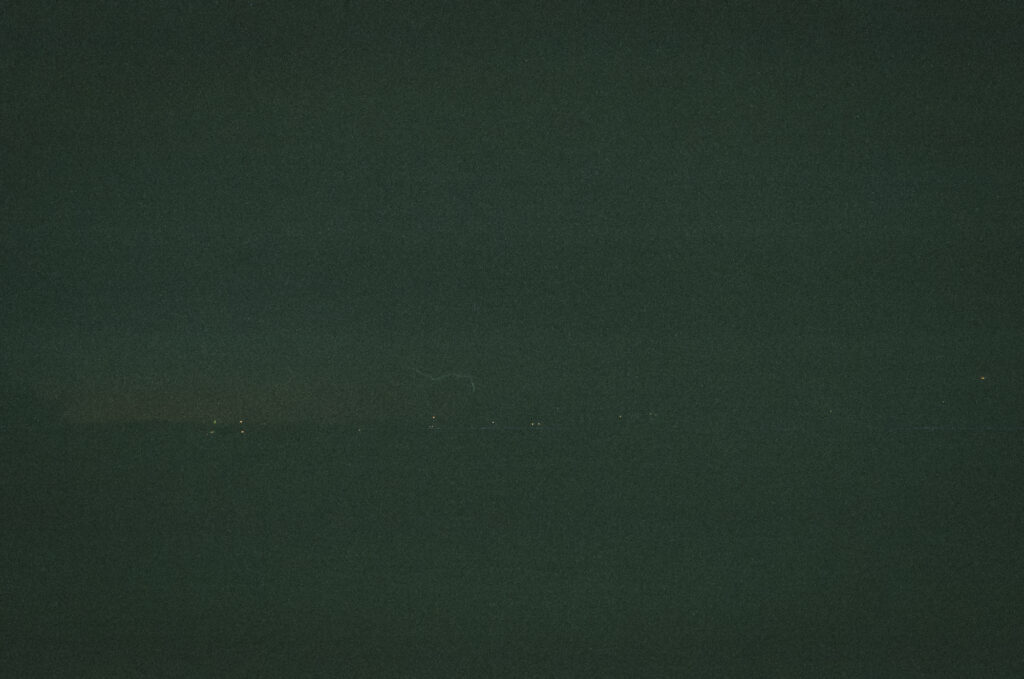
夜の小さな光を見つめていると
私にも帰るところがあったような気がする。
北が、呼んでいる。
北が呼んでいる
( Nordic Journal )
2025.03.03
Text & Photography : lumikka


